スタディピアは、日本全国の短大・大学・大学院を検索できる情報サイトです。
短期大学と大学、大学院はどれも名前が似ていますが、修業年限、入学資格などが異なっています。
スタディピアでは、日本地図から都道府県名を選択し、地域を選んでいくだけで、その場所にある短大・大学・大学院を一覧表示します。さらに、各学校のページには、その学校の所在地をはじめ、電話番号、交通アクセスなどを掲載。気になる学校の情報をご確認いただけます。
短大・大学とは
「短大・大学とは」では、教育機関の一部である短期大学と大学を解説しています。
高校卒業後の進路先、社会人になってからの学び直しなどとして、短大・大学に通う方は少なくありません。
まずは短大について、その魅力、受験方法、得られる学位をご紹介します。
目次
短期大学の魅力

4年生大学と比べて修業年限と取得単位が半分の短期大学ですが、実践学習が多く受けられる分、卒業と同時に即戦力として社会の現場で活躍できます。なお、医療系短大は3年制で、93単位以上の取得が卒業のために必要です。
資格の取得支援
資格を取得するためのカリキュラムが組まれている他、卒業と同時に無試験で資格が取得できたりと、支援体制が充実しています。
もちろん、試験を受けて取得しなければならない資格に対しては、対策講座を別途開講したりすることもあります。
就職に強い
多くの短大で、すでに1年次から就職を意識した指導を取り入れています。就職率は、軒並み80%後半から高い短大では90%中盤の高い水準です。
集中型の学習
短期大学というくらいですから、4年制大学に比べて短い学生生活を送ることになります。その中で必要な単位を取得し、場合によっては資格取得の勉強もしなければなりませんし、就職活動もすぐにスタートします。すべてが集中的に進みますが、その分密度の濃い勉強が行なえるという見方もできます。
学費が安い
4年制大学の半分の期間だけキャンパスに通うので、学費や通学交通費の面でもコストがかかりません。また、一人暮らしをするための生活費も半分になるので、経済的な負担は軽くて済みます。
少人数生講義
大部屋で講義を聴くことはほとんどなく、多くが少人数クラスに分かれて勉強します。必然的に教授と学生の距離が近くなるので、分からないことも丁寧に教えてもらうことができ、勉強の面白さに気付く学生も多いようです。
共学制
短大は女子の進学先という考えは、ずいぶん前の話です。集中的な学びでスキルアップできる点が男子にも高く評価され、今や共学のキャンパスも増えました。男女間のコミュニケーションが互いの視野を広げることにも貢献しています。
受験方法

基本的には、一般入試と推薦入試、AO入試ですが、2004年(平成16年)度から短大でもセンター試験の利用入試を行うようになりました。AO入試は、学力よりも「学びたい」という本人の熱意や目的意識を重視した試験で、書類選考と面接試験が一般的です。
得られる学位

修了後は、短期大学士という学位が授与されます。これは2005年(平成17年)の学校教育法改正により定められた学位です。
大学の定義
日本の大学進学率は、増加傾向にあります。入学希望者総数が入学定員総数を下回る「大学全入時代」とも呼ばれていますが、大学とはどのような場所なのでしょうか。その法律的定義と入学資格、概要についてまとめました。
法律における大学と入学資格

日本の大学は、教育基本法や学校教育法などの法律によって定義され、また入学資格も定められています。
法律における定義

まず、1948年(昭和23年)に制定された「教育基本法」。教育の目的が綴られた教育基本法では、「第二章 教育の実施に関する基本」の第七条で大学に関する記述があります。それによると、「大学は、学術の中心として、高い教養と専門的能力を培うとともに、深く真理を探究して新たな知見を創造し、これらの成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与するものとする。大学については、自主性、自律性その他の大学における教育及び研究の特性が尊重されなければならない」。
次に、学校について規定している「学校教育法」 について見てみましょう。1947年(昭和22)年の制定以来、幾度の改正がなされた学校教育法を引用すると、「大学は、学術の中心として、広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究し、知的、道徳的及び応用的能力を展開させることを目的とする。大学は、その目的を実現するための教育研究を行い、その成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与するものとする」(第九章第八十三条)。
つまり双方の法律で使われている用語を用いると、大学とは「学術の中心」であり、「教育」と「研究」を通して、「成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与する」場所。これが日本における大学の法律上の定義だと言えます。
入学資格

日本の大学(短期大学を含む。大学院を除く)に入学するには、文部科学省が認める「学校教育法」の規定に該当しなければなりません。規定には、例えば以下のようなものがあります。
- 高等学校または中等教育学校を卒業した者(法第90条第1項)
- 特別支援学校の高等部または高等専門学校の3年次を修了した者
(法第90条第1項) - 外国において、学校教育における12年の課程を修了した者(12年未満の課程の場合は、さらに指定された準備教育課程(文部科学大臣指定準備教育課程一覧)または研修施設(文部科学大臣指定研修施設一覧)の課程等を修了する必要がある。)
(施行規則第150条第1号、昭和56年文部省告示第153号第2号)
その他、全12項目のうちいずれかに該当して初めて、大学進学資格として
認められます。
概要と体系

日本の大学には、様々な種別や学習課程が存在します。また大学教育は、高校での教育と比較して、様々な特徴があります。
種別と大学数
大学の種別

日本の文部科学省の定める高等教育機関は、以下の6つの種別が存在します。
- ①国立大学法人等
- ②公立大学
- ③私立大学
- ④短期大学
- ⑤専修学校・各種学校教育
- ⑥高等専門学校(高専)
このうち①~③が一般的に大学と呼ばれ、その多くが4年制です。大学には昼間課程の他に、夜間課程、通信制などもあります。
大学数と学生数
平成23年度の大学数は日本全国で780あり、うち国立大学は86、公立大学95、私立大学599という内訳です。同じく平成23年度の大学生数は2,893,434人でした。昭和60年は大学数460、大学生数は1,848,698人だったことを考慮すると、大学生人口は年々減少しているにも関わらず、大学数は増えていることが分かります。まさに大学全入時代と言えるでしょう。
※2011年8月4日発表の文部科学省 発表データによる
高等教育との違い

大学では高校と異なり、学生の教育課程と修了要件の充足に応じて学位が授与されます。その他、大学ならではの特徴には以下のようなものがあります。
総合科目と専門科目
専攻や学部にかかわらず、人文・社会・自然科学などを幅広く学ぶ総合科目。主に1・2年次で履修し、大学によっては教養科目、一般科目などと呼ばれています。反対に専門科目は所属する学部・学科の分野を深める科目で、いくつかは1年次より履修します。
第一外国語と第二外国語
日本の多くの大学では、第一外国語の英語に加えて、第二外国語を学ぶ授業があります。第二外国語はフランス語、ドイツ語、中国語、スペイン語などから選択し、基礎から学んでいきます。
単位制
大学ではすべての科目に単位数が設定されています。授業に出席し、レポート提出や試験に合格すると単位を取得することができます。必要な単位が取得できないと、進級や卒業ができません。
ゼミ
ゼミナールの略で、専攻分野の中でも、さらに興味のあるテーマを掘り下げていく授業を指します。授業は10人前後の少人数が集まり、討論や実験を通じて自主的に研究を進める形式で行われます。3・4年次に開講されるのが大半ですが、近年は早くから取り組む大学数も増えています。
卒業論文
所属するゼミや研究室で行ってきた研究をもとに、卒業時に執筆する論文を指します。
短大・大学・大学院の基本情報・知識
目次
大学の基礎知識
大学に入学するために
- 大学選び
- 大学の費用
大学生の学校生活
- 大学の学び
- 大学の授業構成
- キャンパスライフ
- 留学
大学生の進路
短期大学の基礎知識
- 短期大学とは
- 短期大学の種類
- 短期大学の学び
- 短期大学卒業後
- 資格取得や学生生活など
短大・大学・大学院のブログ情報
地域別に短大・大学・大学院を探す
短大・大学・大学院名を入力して探す

徒歩3分(240m)以内にある賃貸物件を検索できます。

賃貸物件が検索できます。
短大・大学・大学院の生活便利情報
短大・大学・大学院に関する用語の解説を掲載しておりますので、ぜひご覧ください。
短大・大学・大学院用語辞典
短大・大学・大学院に関連する施設検索
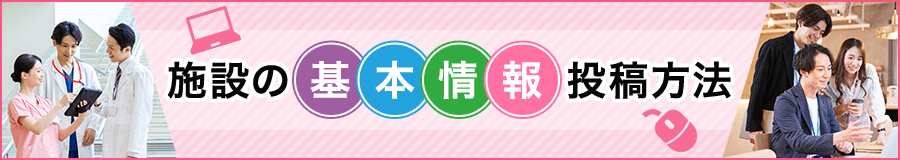
投稿をお待ちしております。






















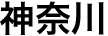
















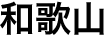




















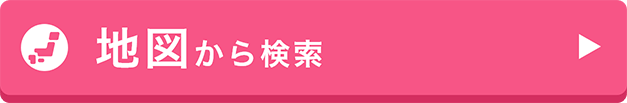
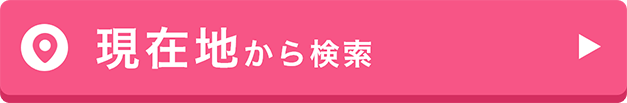
























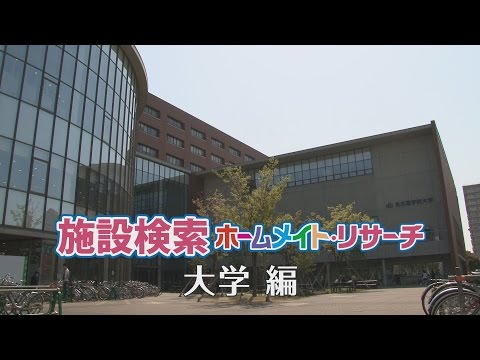

 SNS公式アカウント
SNS公式アカウント
