冬の大学情報
この冬こそ!学ぶ意欲が高まったら通信大学へ行こう!/ホームメイト
通信制の大学で勉強を始めてみませんか。通信大学では、大学卒業資格である「学士」取得が目指せます。時間的・地理的な制限も少なく、自宅に居ながら学習を進めることができるので、無理なく始めることが可能です。スクーリングの必要が全くない通信大学もご紹介。幅広い知識を身に付け資格習得を目指しましょう。
学部と取得資格の豊富さも通信大学の魅力のひとつ
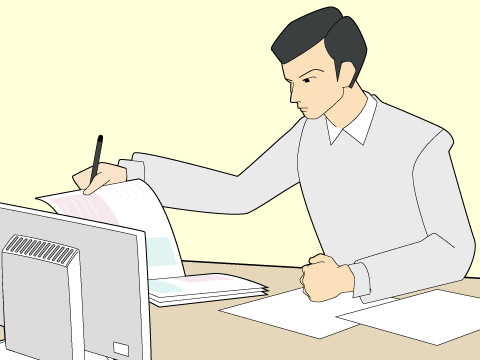
通信制の大学は、通学制に比べて、年間の学費が8~30万円と安いことや、時間的・地理的な制約が少ないこと、入学時の選考において学力試験を実施しないということが大きな特徴です。4月に入学したいなら、ちょうど冬から出願が始まります。今こそ、通信大学で新しい学びを始めてみましょう。
通信大学は、通学制と同じように資格習得が可能です。大学や学部ごとで違いはありますが、習得できる資格は、「教員免許状」や「司書」、「幼稚園教諭」や「学芸員」など。また、司法試験や公認会計士試験などの国家資格の受験資格が得られます。通信大学は学部も豊富で、心理学や教育、福祉、ビジネスなど、様々な分野の学びが可能です。
日本大学 通信教育部
日本最大級の通信教育部。「法学部」、「文理学部」、「経済学部」、「商学部」など4学部8学科。「教員免許状」や「司書」、「学芸員」の資格習得が可能です。
京都造形芸術大学 通信教育部
芸術系を学びたい人にはおすすめ。「芸術学科」で4コース、「美術科」で5コース、「デザイン科」で4コースの合計13のコースを展開。通学不要のインターネット学習がメインの「手のひら芸大」と自宅学習+週末スクーリングがメインの「週末芸大」コースがあります。
武蔵野大学 通信教育部
2学部8コース。医療や福祉、児童教育など人の役に立つ仕事に就きたい人におすすめ。「人間科学部」では「認定心理士」や「アメニティスペシャリスト」。「教育学部」では「小学校教諭一種免許状」などの資格取得ができます。
通信大学を選ぶときに気を付けたい2つのポイント
通信制の大学を選ぶ際に注意したい点が2つあります。ひとつめは大学の「授業形態」です。授業形態は、「テキストメイン」、「スクーリングメイン」、「インターネットメイン」の主に3タイプがあります。「テキストメイン」とは、印刷教材等を利用して学習し、添削指導を受けて学習を進める授業形態です。通信制としては、昔ながらの授業形態と言えるでしょう。「スクーリングメイン」とは、印刷教材等だけでなく、面接授業が行なわれる授業形態です。大学へ通学し、直接講師に指導してもらえる点が魅力。スクーリングの回数は、年に数回だけ、毎週など、大学や学科によっても異なります。「インターネットメイン」とは、インターネットで授業を行なう授業形態です。疑問があれば、オンラインで即答してもらえるので、学んだ内容が直実に身に付きます。単位認定試験もオンラインで行なわれ、通学の必要が全くない大学もあるようです。
2つめに注意したい点は、「卒業実績」です。卒業生数や割合をよく確認しましょう。なぜなら、通信大学は、卒業が難しいと言われています。ほぼ一人で勉強を進めていかなければならないので、途中から勉強についていけなくなることが第一の理由です。卒業実績が高い大学ならば、担任制度があるとか、ネット上で学生同士が交流できる場があるなど、サポート体制面も充実していると言えます。
通信大学を選ぶには、どんな授業形態が自分に合っているのか、「卒業できる大学」なのかを見極めることが重要です。
スクーリングの必要がない通信大学
「仕事が忙しい」、「小さな子どもがいる」など、大学へ通うのが難しい理由がある方でも、大学卒業が可能になる、スクーリング不要な通信大学をご紹介します。
サイバー大学 IT総合学部
ソフトバンクグループの大学で、独自のプログラムで人材育成を目指します。授業や試験などは、すべてインターネット上での受講が可能です。卒業時には、学士はもちろんIT分野の資格を取得できます。
ビジネス・ブレークスルー大学 経営学部
ビジネスマン向けの大学で、経営について学べます。講義を受講後には、オンライン上でディスカッションを開始するユニークな講義があるのが人気です。
放送大学 教養学部
幅広い知識を学べるように6つのコースに展開。学士はもちろん、大学が独自で行なっている学習プログラムに基づき、修了者に対しては「証明状」や「科目履修認証明カード」が交付されます。



冬はクリスマスや年越し、新年など、大学生にとっても心躍るイベントが続きます。一方で、目前に迫る新年度を前に、大学では様々な手続きや試験が行なわれる慌ただしい季節でもあります。
社会人特別入学試験

生涯学習に重きが置かれる昨今、大学における社会人の受け入れも必要不可欠となっています。特定の学部やコースなどで、社会人を特別枠として受け入れるために、概ね秋から冬にかけて各大学で実施されるのが、社会人特別入学試験です。社会での経験を積んだ人が、学問への新たな関心や自己実現、社会的責務などへの意欲を高めて大学への入学を目指す際の門戸になります。
出願資格は、高等学校または中等教育学校を卒業した人、もしくはそれと同等の学力を有する人なら誰でも受けられる場合や、ある一定の社会人経験を求める大学まで様々です。選抜の方法としては、書類審査の他、小論文や英語、面接など大学ごとに設定した試験により選抜します。
学部やコースごとに若干名しか募集しない大学が多く、狭き門となっています。
帰国生入試
海外での就学経験を持つ帰国生を対象にした帰国生入試は、多くの場合、秋から冬にかけて実施され、遅いケースでは4月入学の直前である3月まで試験が行なわれます。この試験は、異文化体験で身に付けた個性や、海外の教育環境の下で培われた多様な教養、知識、能力などを評価することで、特別枠として入学を認める試験制度です。
帰国生を対象とした合格基準には、大きく3つのパターンがあります。
ひとつは、滞在国の統一試験や外国語試験のスコアなどを重視する試験です。当日の筆記試験や面接試験に重きを置く大学、さらにその両方を平等に加味して合否が決まります。
滞在国の統一試験とは、アメリカはSAT、イギリスはGCE、オーストラリアはHSC、IBなどのスコアです。外国語試験としては、TOEFLやTOEIC、英検など。当日の筆記試験は、小論文、英語(外国語)をはじめ、学部によって現代文、数学、理科などを組み込んでいる大学もあります。
帰国生入試出願条件
帰国生入試を受験する際の条件は、大学や学部、コースによって異なります。主には、海外の学校への在籍期間を定めて制限をしている場合や、海外の教育課程に基づく学校を卒業しているか否かを問う場合があります。また、保護者の海外赴任や移住に伴う渡航ではなく、単身での留学の場合、帰国生入試枠に含まれない場合もあるので確認が必要です。
奨学金制度
大学での学習活動に打ち込むために重要となるのが、奨学金制度です。奨学金には様々な種類があり、大学が独自に設けている奨学金制度をはじめ、日本学生支援機構の奨学金などがあります。
日本学生支援機構奨学金とは、日本全国の学生が利用する貸与型の奨学金制度。無利子で受けられる第一種と有利子にて支援が可能な第二種の奨学金があり、どちらも卒業後に返還しなければなりません。
日本学生支援機構の貸与型奨学金を受けている学生にとって、冬の時期に必要な手続きがありますので、注意が必要です。
大学1年生から3年生にとっては、毎年冬の12月から1月に、次年度継続希望者を対象とした継続説明会が開かれます。継続手続きを怠ると、奨学金の資格を喪失してしまいます。また、大学の最終学年で貸与満期終了の予定者には、秋から冬にかけて返還に関する説明会や返還に関する書類の提出が求められます。いずれも重要な手続きになりますので、忘れずに行ないましょう。
その他にも、大学が独自に行なっている奨学金の制度を利用する場合、夏に出願を行ない、その後選考を経て冬に採否の通知が来るという流れが多いので、奨学金を希望する場合は、民間の奨学金制度も含めて条件などを比較しながら、必要な手続きを行なって下さい。
日本学生支援機構の奨学金(国内)の種類
国内の大学院、大学、短期大学、高等専門学校、専修学校(専門課程)に在学する学生、生徒を対象にした無利息の第一種と、365日あたり3%を上限とする利息付きの第二種があります。第一種は特に優れた学生及び生徒で、経済的理由により著しく修学困難な人に貸与するもの。貸与額は、学校種別や設置者、入学年度、通学形態などによって定められます。第二種の貸与額は、5種類の貸与月額から自由に選択できます。
大学生の冬の過ごし方は、多岐に亘るでしょう。長い冬休みを利用して海外旅行に出かける人がいる一方で、地方から出て来ている学生は実家に戻りゆっくり過ごすかもしれません。スポーツに励む人や成人を迎える人などもいるでしょう。大学生だからこそ過ごすことができる貴重な時間、有意義に活用したいですね。
箱根駅伝

関東学生陸上競技連盟が主催する箱根駅伝は、お正月の1月2日、3日の2日間にかけて行なわれ、関東の大学生チームのみが参加できる駅伝です。東京から箱根までの往復217.1kmを往路と復路に分け、合計10区間のタイムで競う学生長距離最大の駅伝競走です。往路と復路、そして総合の優勝校が決められます。コースは東京を出発して、戸塚、平塚、小田原等を経由して折り返し地点となる箱根へ。そして翌日、箱根からスタートし、同ルートを経由してゴールとなる東京へ向かいます。小田原から箱根へ向かう第5区は高低差800m以上。この5区を快走することで“山の神”と名付けられる選手もいます。
沿道には多くの人が応援につめかけます。往路のゴールと復路のスタートとなる箱根には、箱根駅伝を見るための観光客が毎年大勢集い、選手に温かい声援をかけています。本大会の10位までが来年の大会に参加できるシード権を獲得するため、ゴール前では熱い闘いが繰り広げられます。また、公道を使用するため走ることができる制限時間が決められており、時間内に到着しないと次の走者は一斉繰り上げスタートとなってしまいます。チームのたすきをつなげることができないという点から、毎年熱くも切ないドラマが生まれる場面でもあります。2日間に渡りテレビで生中継されるため、年始から熱く清々しい姿を家庭でも見ることができます。
成人の日
1984年(昭和59年)に設けられた、成人を祝う国民の祝日です。1999年(平成11年)までは、1月15日でしたが、ハッピーマンデー制度導入に伴い、2000年(平成12年)から1月の第2月曜日となりました。同日には、全国各地で成人式が開かれます。前年の成人の日の翌日から、その年の成人の日までに誕生日を迎える人を対象にしていましたが、最近では前年の4月2日からその年の4月1日に成人する人を対象にしている場合が多くあります。そのため、華やかな衣裳をまとい、成長した姿をお互いに見せ合う同窓会であるとも言えます。各地方公共団体で講演や催しなどが行なわれ、記念品などが贈られる場合もあります。千葉県浦安市では、人気テーマパークのディズニーランドで開催されることでも有名です。しかし、近頃では、喜びを体現し過ぎてしまう成人も多く、ふるまいやマナーについて問題視されています。昔は、成人を祝う儀式として、男子には元服・褌祝、女子には裳着・結髪が行なわれていました。
お雑煮
お正月に一年の無事を祈りながら食べる、餅の入った汁物の日本料理のことです。祝い事や特別な日である「ハレの日」の食べ物として知られる餅。新年には、餅をついて神様にお供えをしており、そのお下がりを頂くことでご利益を頂いたものが「雑煮」と言われています。今のようなスタイルになったのは、室町時代頃からだそうです。
沖縄を除く日本各地で食べる風習があり、地方によって見た目、味ともに異なるため、各地から集う大学生にとっては話のタネになるのではないでしょうか。例えば、主役となる餅は丸餅か角餅かに分かれ、丸餅は京文化を受けた土地、角餅は江戸の文化を受けた土地に多いと言われています。また、その餅を焼くのか、焼かずに煮込むのか、焼いてから煮込むのか、または茹でるのかなど調理法にも違いがあります。汁も地方によって変わり、一般的にすまし汁の割合が多いと言われていますが、関西地方は白味噌を用いたものが多く、その他、赤味噌仕立てのものや小豆汁の地域もあります。
卒業が間近に迫って、大学の最終学年では卒業論文の提出時期がやってきます。大学によって記述方法や提出方法は様々ですが、自分でテーマを決めて書き上げる卒業論文は、4年間の集大成でもあります。また、3年生は卒業後の進路を考えるときです。就職する人が多い中、キャリアアップのために大学院に進学する人も増えてきました。進路のひとつとして検討してみてはいかがでしょう。
卒業論文

卒業を間近に控え、最終学年は卒業論文(卒論)の提出に向けてラストスパートの時期です。卒業論文は、卒業研究の成果として提出する論文で、通常はこれを提出して最終的な単位を取得し、卒業となることが多いようです。文系の学部では、ゼミナールの論文をもって卒業論文に代えるところもあり、大学や学部によって提出形態は様々で、必修でない場合もあります。理系の学部では、卒業研究や卒業制作という形を取り、これが卒業論文と同じ扱いになります。医学部では、卒業のために論文や研究ではなく卒業試験が実施されます。また、芸術系の学部は、美術系では絵画やデザインなどは卒業制作、音楽系は卒業発表会や卒業演奏会が、卒業のための成果発表として行なわれます。
卒業論文は、学生が自分で研究するテーマを考え、それに必要な資料収集やインタビューなどもこなすのが基本です。提出する際の文章量は大学によって規定され、それをクリアしないと単位を取得できない場合もあります。
卒業論文の提出時期は大学や学部によって様々ですが、2月から3月を提出期間としている大学が多く、提出後に、教授から口頭試問によって理解度の確認が行なわれる場合もあります。理学部や工学部、農学部などでは、研究成果をOHPやコンピューターを使ってプレゼンテーション・スタイルで発表するところもあります。
近年では、パソコンを使って卒業論文を制作することが多くなり、資料や情報の収集もインターネットを利用するケースが多いようです。ただし、文章をそのままコピー&ペーストで持ってくるのは評価を下げられるため、参考文献の引用を用いて、自分の意見や考えを述べるのが大切です。また、文章だけでなく図や表を上手く活用して、見せる工夫も重要なポイントになります。
なお、苦労して書いた卒業論文もコンピューターのトラブルなどでファイルが消えてしまっては元も子もありません。必ずバックアップを取っておくようにしましょう。
大学院への進学

大学卒業後の進路として、多くの人が就職を考えていますが、大学院へ進学する人も最近では増加しているようです。これまでの大学院は、学部卒業生がさらに専門的な研究を行ない、「研究者を養成する場」というイメージがありましたが、現在はこれに加えて、社会で即戦力として活躍できる「職業人を養成する場」となっています。特に、2003年度以降に設立された法科大学院や会計大学院など専門職大学院は、その分野での様々な研究を行ない、高度な専門知識を身に付けることを目的としています。そういう意味では、学究目的より実務的に役立つことを学び、社会ニーズに対応できる人材育成が大学院に求められているとも言えます。また、大学院へは社会人を経験してから入学する人も多くいるので、実社会の話や企業の動向などを直接知ることができます。
大学院への進学を希望する場合、自分が進みたい方向性や学ぶ目的を整理する必要があります。目的意識がはっきりしたら、どこの大学院を目指すのかを具体的にし、志望校を選びます。志望校選びは、自分の学びたい内容を学べる場なのか、資格取得ができるか、自分にとってプラスになることが多いか、学習環境や立地などはどうかなど、様々な角度から選んでいきます。ある程度志望校を絞り込んだら、ホームページを見たり資料請求をしたりして、情報を集めましょう。通っている大学に大学院が併設されていれば、研究室を訪ねたり、教授や講師に聞いたりすることができるため、積極的に情報を入手します。志望校が決まったら、入試制度を確認し、入試までのスケジュールを作ることで入試に向けた準備に入ります。
大学院への進学は、以前程ハードルも高くなく、学習意欲さえあれば実現できますので、進路の選択肢のひとつとして考えておくと良いでしょう。









